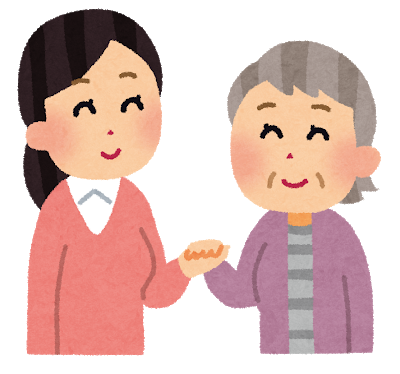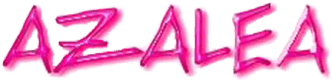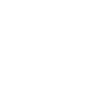他人に対する不正を防ぎうるのは、正義の原則よりもむしろ思いやりである。
by エリック・ホッファー
あなたは、他人を説得しようと試みていませんか?
タイトルの言葉は、アメリカの社会哲学者 エリック・ホッファーの言葉です。
他人が何か悪いことを企んでいるとき、それを防ぎうるのは、正義の原則を訴えることよりも、思いやりだと述べた深いメッセージですね。
私たちは、たとえば不正なことをしようとしている人や、悪い行いをしようとしている人を思い止まらそうとすることがありますよね。
もしくは、悪い行いをした人を説得して、反省を促すことが必要になることもあります。
親が子供に対して、先生が生徒に対して、上司が部下に対してなど、さまざまな場面が想定できますが、いずれにしても、彼らの悪い行為を思い止まらせる、または反省させる必要に迫られることがあります。
そんなとき、私たちは彼らに対し、正義の原則や常識などによって説得しようと試みますが、うまくいかないことが多いような気がします。
なぜ、正義感を振りかざしても、彼らの心は動かないのか?
それは、人間は理屈では動かないからです。感情によって行動することが多いのが実情です。
彼ら自身も、自分が悪い行いをしている、もしくはしようとしていることはわかりきっているはずで、今さら正義感で説得されても聞く耳を持たないのが現実です。
ではどうするのか?
それは、その人の感情、思いやりに訴えかけるのです。
そんなことをすれば、誰かに迷惑がかかるとか、誰かを悲しませてしまうなどと、その人の心に訴えかけると、意外とあっさりと心変わり、反省することが多いのです。
しつこいようですが、人は理屈で動くのではなく、感情で動くのです。
自分にとって不都合なことや嫌なことはしたくないものなのです。
反対に、自分にとって都合のいいことや、喜ばしいことは積極的にしたくなるものです。
だとしたら、彼らの琴線に触れるような言葉で彼らを説得すれば、うまくいくはずなのです。
理屈ではなく感情に訴えかけることで、人は動くと言うことを常に意識しながら、生きていきましょう。
SDGsは、2030年に向けて、持続可能な社会の実現を目指し、理想的でより良い世界を創り出すために、国連が発表している世界共通の行動目標です。
SDGsの17の目標は、全てが正義の原則とも言えるものですが、思いやりの原則とも言えるものかもしれません。
貧困や飢餓、人権侵害や環境問題など、人が人を思いやる気持ちがあれば、このような問題が生じることはないのです。
ましてや、現在も世界各地で続いている戦争やテロなどの紛争は、人と人との争いであり、互いを思いやる気持ちがあれば決して起こることはないのです。
正義感を持っていても、紛争や迫害はなくなりません。なぜなら、人は自分たちが正義であり、相手が間違っていると思い込んでいるからです。
人としての思いやりの気持ちを持ち続けていれば、SDGsの目標も容易に達成できるのかもしれませんね。